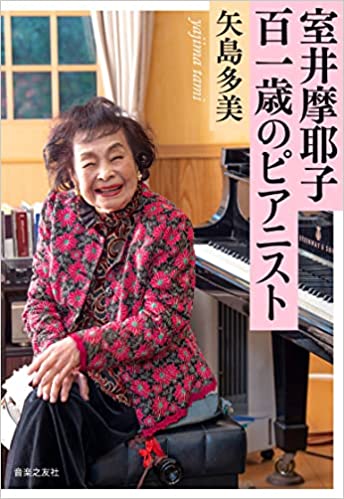[ ]ピアノのメンテナンス費用の矛盾
従来のピアノのメンテナンス費用は矛盾が多く含まれています。
例えば調律料金は地域差がありますが¥15.000~¥20.000と大体の相場が決まっています。
本来は調律師の技術レベルでメンテナンスの品質も料金も異なるのが本来の姿だと思いますが、仕上げの品質の違いがわからないお客様が多いので、大体一律料金になっています。
しかし技術レベルの高い調律師なら調律の所要時間が1時間少々で完了し、音程も正しく調律も狂い難いのですが、逆の場合は所要時間が長く出来上がった調律も音程も不安定で調律も狂いやすい状態ですが、現状は同一料金になっています。

弊社の場合は調律だけでなく調整や整音を含め半日かけたメンテナンスが多いのですが、技術レベルの高い調律師なら半日でも普通の調律師の1日分以上の作業量を行い、尚且つ仕上げもほぼ完ぺきになります。


ピアノの性能を大切にお考えの方に、下記の資料2点を無料進呈しています。
資料の詳しい案内はこちらから
グランドピアノの3日間の出荷調整作業を動画でお見せしていますが、丁寧な調整でいかなるピアノであれ性能が大幅に向上することがご理解頂けます。DVD全24分
ネット上では公開できない業界の矛盾点や裏話を満載。全44ページのピアノ選びの新しいバイブルです










 0120-174-016
0120-174-016