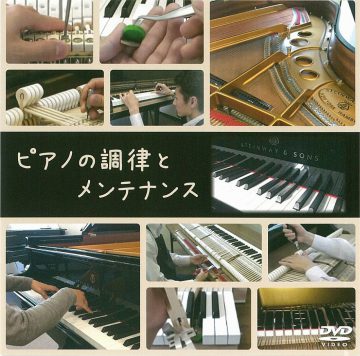[ ]力強い弾き方、繊細な弾き方をされる方のエピソード
その昔、弊社でホロビッツが弾いていたというニューヨークスタインウェイの展示試弾会をした時の話ですが、弊社のスタインウェイユーザーの75歳の女性も試弾に来店され、ご高齢なので彼女をバスターミナルまでお送りした車の中で聞いた話です。
彼女の後に試弾された方は芸大卒の新鋭のピアニストでしたが、たまたま彼の演奏を聴いた彼女が、車の中で「弾き方が荒いわね~」と仰いました、私はさすが芸大卒だけあって「難しい曲をパワフルに演奏するなあ~」という印象でしたが75歳の方から「荒いわね~」と云われたのが強く印象に残っています。
ニューヨークスタインウェイとハンブルグスタインを使った聴き比べコンサートの様子

現役の音大生にスタインウェイを購入して頂いた時の話ですが、納入後スタインウェイの感想をお聞きしたところ「自分は今まで力強い(パワフル)な演奏をする人だと思っていたが、スタインウェイを購入してから弾き方(繊細に)が変わった」と仰られたことも強く印象に残っています。

これは別にスタインウェイ(高級ピアノ)だからということではなく、たぶん、日頃、自宅で良く調整されたピアノを弾いている方は、無理して鍵盤を叩きにいかなくても十分な音量が出るということが体感的にわかるので自然に繊細な弾き方になるのだろうと推測しています。
過日、小学生のお嬢様がお母様と試弾にご来店、彼女はコンクールにもよく参加されるだけあって、小学生でもとても繊細(感情を込めた)を演奏をされます。部屋の関係でコンパクトなグランドピアノをご希望ということがあり、彼女が選んだのがディアパソンの小型グランドでした。
ご契約の最後にお母さんが心配そうに「ヤマハでなくてもいいの?」と小学生の彼女に聞くと「これがいい」と断言されたのでご契約頂いたんですが、さらに弾き易くするために鍵盤の鉛調整をご提案するとOKだったので、新品ピアノですが鍵盤の鉛調整をしてからお届けしました。

鍵盤の鉛調整が完了後、ディアパソンのテスト演奏をする弊社の伊ヶ谷君

納入後、お母様から以下のメールをいただきました
ディアパソン164R、納入されました。ショールームで弾いた時とは別物に仕上がっていました。どこのホールのフルコン?という感じの弾き心地です。娘は近場のホールはかなり弾いていますが、ホールのピアノより弾きやすい、あったかい音も好き、心地いい、とのこと。鉛調整していただいて大正解でした。
一千万のピアノ、の意味が分かりました。他も丁寧に調整いただいたのだと思います。
ありがとうございます。
ピアノの性能を大切にお考えの方に3点の資料を無料進呈しています。





 0120-174-016
0120-174-016