[ ]ピアノの寿命についてのお話 ⑤
アンティークピアノの場合
一部の愛好家にノスタルジックな魅力で人気があるアンティークピアノ(いわゆる100年物)ですが、フルオーバーホールをすれば味があり魅力的なピアノに仕上がります。
復元されたクララ・シューマン(シューマンの奥さん)が愛用されたと云われる1877年製のグロトリアン・スタインヴェック(劉生容記念 館)です。


岡山市中区湊 劉生容記念 館

ただ弦楽器と違い内部構造が複雑なピアノは、内部に膠(ニカワ)を使った膨大な接着箇所があり、それらは100年かそれ以上昔の接着ですので、それらの接着が突然剥がれる懸念があり、想定外のトラブルが起こる可能性があります。
ですからアンティークピアノは、ファーストピアノではなくセカンドピアノとして大切に使用し、設置環境(温度・湿度)にも特に気を使う必要があります。
またトラブルがひとたび起これば、その修理に面倒な手間がかかることが多いので、アンティークピアノのメンテナンスは引き受けないという調律師も多いので維持管理費用を含めて細心の注意が必要です。
余談ですが、ある高校の創立100周年記念の行事として、当時、高校にあった1880年代のスタインウェイをメーカー(ハンブルグ工場)に送ってフルオーバーホールしたことがあります。
この時には消耗品はもちろんですが、響板やアクションまでそっくり新品に交換して、以前のピアノで使ったのは外装のケースとフレームのみでしたが、後々まで責任があるメーカーだからやったのだと思いますが、100年以上経過した古いピアノでもここまでやれば安心ですが、修理費用も新品の価格並みになりました。
上記の 劉生容記念 館は、元々、絵画を展示・保管するする目的の建物で湿度・温度は適切に管理されているので、アンティーク・ピアノの保管場所にも適しています。
ピアノの寿命

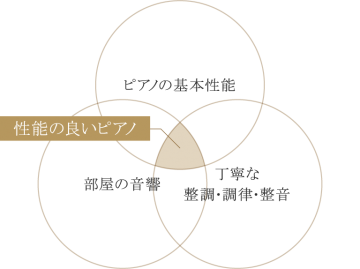




 0120-174-016
0120-174-016







