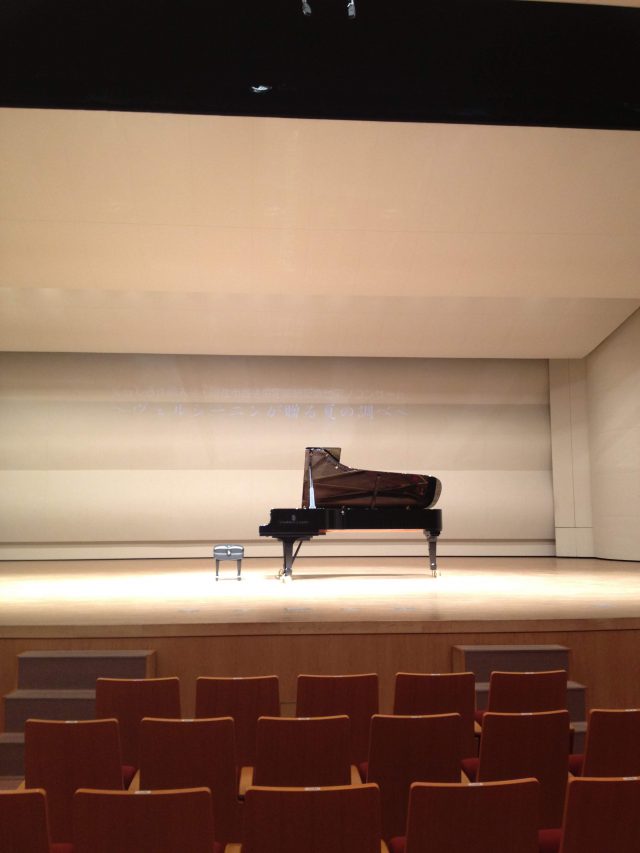[ ]ピアノ4時間調整×4日コース 4日目 (最終日)
ヤマハG3の全16時間コース最終日です。これまでの内容はこちらから↓
・グランドピアノ4時間×4日コース初日目
・グランドピアノ4時間×4日コース2日目
・グランドピアノ4時間×4日コース3日目
弦の振動を止める役割のダンパー。
鍵盤・アクションの調整が終わったら次はダンパーのかかり(始動)と総上げの調整です。


少しだけ今回のダンパー作業風景を動画に撮ってみたのでこちらをご覧ください。
(もっと詳しく知りたい方はこちらの→動画で解説してます)
次はダンパーペダルの踏み込み量の調整とダンパーをストップさせるバーの高さの調整をしました(写真が撮れてませんでした)

次はソステヌートペダルの調整です。
ソステヌートのバー(ロッド)の前後と高さの位置調整をしました。
ソステヌートペダルの仕組みと使い方は先日動画をアップしていますので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


次はシフト(ソフト)ペダルの踏み込み量の調整です。
右の拍子木のストッパーネジを出したり引っ込めたりして動く量を調整します。
一番左の弦がギリギリ外れるくらいの量で調整しています。


弦が当たっているポジションを把握するためにカーボン紙を使ってハンマーに色を付けます。
シフトペダルを踏んでも効きが悪い時は、ハンマーに針を刺してソフトな音を作ります。


次はハンマーと弦の噛み合わせの調整です。
ハンマーを弦に付けた状態で弦を1本ずつ弾き(はじき)3本(または2本)の弦に同時に当たるようにハンマーを薄っすら削って高さを調整します。
同時に当たらないときれいに発音することができません。この調整で整音の8割が完了します。

最後に音の硬さを揃えるために硬い音だけをピックアップしてハンマーの肩の部分に針を刺して硬さを調整します。

音色の確認が終わったのでペダルも磨きました。
本日のメニューは、
①ダンパーかかり調整
②ダンパー総上げ調整
③ダンパー踏み込み量調整
④ダンパーストップレール調整
⑤ソステヌート位置調整
⑥シフト(ソフト)ペダル踏み込み量調整
⑦シフト(ソフト)ペダルの整音
⑧弦あたり(3弦合わせ)調整
⑨ハンマー弾力調整
⑩ペダル磨き
⑪譜面台クロス貼り替え
でした。とりあえず全体をざっと調整することができました。
細かいところをいえば、ダンパーをダンパーアクションごと解体してワイヤーを磨いたりクロスの硬さを調整したり、ペダルを解体して錆びを取ったり磨いたりともっとやることはありますが、16時間ではとても時間が足りないので今後のメンテナンスの際に少しずつ行なうことになりました。今回はお客様のご要望を優先し、それに沿ったメニューを時間内で調整して行ないました。
結果は、大変満足いただきさらに帰宅後メールで
「弾いた時の音の気持ちよさは勿論、和音を弾いて音が減衰した頃にそっとペダルを離した時の音の綺麗さ。レッスンが楽しくなります」と喜びのメールをいただきました。嬉しいですね。ありがとうございました。
>>>ピアノのコンディションを良くするために必要なこと
①全体の調整 ②空調管理

無料資料の詳しいご案内はこちらから










 0120-174-016
0120-174-016